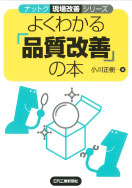| |
|
| |
第1章 モノづくりと製造品質 |
| |
1-1 品質が良くなると製造原価は安くなる |
| |
1-2 日本でのもの作りと品質向上の歴史をひもとく |
| |
1-3 物づくりの品質は設計品質と製造品質に大別できる |
| |
1-4 良い製造品質を現場力で作り込む |
| |
1-5 5Sで現場力の基礎を固める |
| |
1-6 品質改善に役立つ実績データの見方と表し方 |
| |
1-7 不良とは「ばらつき」である |
| |
1-8 製造現場でばらつきが発生する2つの理由とは |
| |
コラム(1) 製造会社の必携条件は良い品質、良い環境、安い原価 |
| |
|
| |
第2章 製造品質を決定する5つの要因 |
| |
2-1 製造品質を良くするには2つの方法がある |
| |
2-2 5つの要因を見える化する |
| |
2-3 人の力量をアップしてばらつきを減らす |
| |
2-4 機械設備の故障をゼロにする |
| |
2-5 材料、作業方法、測定のばらつきも減らす |
| |
2-6 工程で製造品質を作り込む |
| |
2-7 最適な作業方法を確立する |
| |
2-8 品質を作り込む上で重要な作業を標準化して維持管理する |
| |
2-9 工程能力指数で製造品質を数値化する |
| |
2-10 製造品質を保証する |
| |
2-11 検査で製造品質を保証できるか |
| |
2-12 製造現場の品質保証活動とは |
| |
2-13 製造物責任(PL)法へ対応する |
| |
コラム(2) 保証と保障と補償の使い分け |
| |
|
| |
第3章 製造品質改善に必要な心・技・体 |
| |
3-1 心・・・お客さまの目線で見る |
| |
3-2 お客さまから見た当たり前の品質、一元的な品質、魅力的な品質 |
| |
3-3 明日に向かって発想する改善マインドを持つ |
| |
3-4 技・・・製造品質改善での活用手法 |
| |
3-5 品質改善の手順を標準化する |
| |
3-6 品質改善にQC7つ道具を活用する |
| |
3-7 品質改善に新QC7つ道具を活用する |
| |
3-8 品質改善に役立つ統計手法の中身を探る |
| |
3-9 管理技術の東の横綱であるIEとは |
| |
3-10 管理技術の西の横綱であるVEとは |
| |
3-11 効率的にアイデアを発想しよう |
| |
3-12 体・・・組織や小集団活動を活用しよう |
| |
3-13 小集団によるサークル活動でパワーアップしよう |
| |
コラム(3) 父親の身長と息子の身長は相関するか? |
| |
|
| |
第4章 現場でできる製造品質改善の進め方(Ⅰ) |
| |
4-1 品質改善の対象となる問題・課題を把握する |
| |
4-2 重点指向で問題・課題を絞り込む |
| |
4-3 3現主義で現状の実態を把握する |
| |
4-4 層別により集めたデータを分ける |
| |
4-5 パレート図を活用して重点指向を推進する |
| |
4-6 改善目標と日程を決定する |
| |
4-7 不良には必ず要因がある |
| |
4-8 要因を見逃さないために特性要因図を作成する |
| |
4-9 主要因をデータで確認する |
| |
4-10 主要因をヒストグラムで見える化する |
| |
4-11 主要因を散布図で見える化する |
| |
4-12 急げば回れを実践する実験計画法 |
| |
4-13 実験により主要因の最適条件を探る |
| |
4-14 改善の4原則で対策を立案する |
| |
4-15 TRIZを活用して対策案の技術的矛盾を解決する |
| |
4-16 対策会議ではブレーンストーミングを活用する |
| |
コラム(4) 3現主義+2原主義=5現主義 |
| |
|
| |
第5章 現場でできる製造品質改善の進め方(Ⅱ) |
| |
5-1 改善対策を試行する |
| |
5-2 アローダイヤグラムにより実施計画を作成する |
| |
5-3 対策案を実施し効果を確認する |
| |
5-4 品質工程表や作業標準書による歯止めを実施する |
| |
5-5 作業の標準化を実施する |
| |
5-6 品質工程表の作り方と使い方 |
| |
5-7 作業標準書の作り方と使い方 |
| |
5-8 教育訓練を実施する |
| |
5-9 効果をあげる教育訓練のポイント |
| |
5-10 管理図で効果の定着度合いを確認する |
| |
5-11 管理図の作り方 |
| |
5-12 機械化・見える化などにより品質改善状態を維持管理する |
| |
コラム(5) アローダイヤグラムの作成 |
| |
|
| |
第6章 製造品質改善のツボとコツ |
| |
6-1 データのとり方とまとめ方 |
| |
6-2 平均値だけではだまされる |
| |
6-3 ばらつきを数値化する偏差、変動の求め方 |
| |
6-4 要因別にばらつきを分けてみる |
| |
6-5 品質改善に必要な正規分布とは |
| |
6-6 正規分布の特徴を利用しよう |
| |
6-7 品質工程表の作成に必要な工程分析 |
| |
6-8 作業標準書の作成に必要な作業分析 |
| |
6-9 品質改善に役立つレイアウト改善を実践する |
| |
6-10 設備の品質を改善・管理するTPMとは |
| |
6-11 設計品質改善にチャレンジする |
| |
6-12 QFDでお客さまの要求を設計品質に変換する |
| |
コラム(6) 管理図の管理限界線は判断ミスのポカヨケ |
| |
|
| |
第7章 製造品質改善で収益を向上! |
| |
7-1 品質を作り出すコストの中身を探る |
| |
7-2 品質が悪いために発生する失敗コストの中身と求め方 |
| |
7-3 品質を評価するために発生する評価コストの中身と求め方 |
| |
7-4 品質を良くする予防コストの中身と求め方 |
| |
7-5 効率的な収益向上の進め方 |
| |
7-6 失敗コスト低減のツボとコツ |
| |
7-7 評価コスト低減のツボとコツ |
| |
7-8 予防コスト低減のツボとコツ |
| |
|