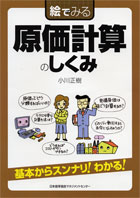書籍詳細
詳細内容
| 第1章 原価計算でなにがわかるんだろう? | |
| ・ なぜ「原価計算」をするのか? | |
| ・ 「どの製品が儲かっているか」がわかる | |
| ・ 「この部品を作るといくらかかりそうか」がわかる | |
| ・ 「部門別や業務別にいくらかかっているか」がわかる | |
| ・ 「購買部門が1回発注すると事務費用がいくらかかるか」がわかる | |
| ・ 「お客さまサービスや品質向上にいくらかかっているか」がわかる | |
| ・ じつは人によって「原価計算の使い方」はさまざま | |
| column① 原価管理の心・技・体 | |
| 第2章 そもそも原価とはなんだ? | |
| ・ 会社が活動すると発生するのが「原価」 | |
| ・ 会社の活動ごとに分類した原価、「製造原価」と「販売費・一般管理費」 | |
| ・ 見ためごとに分類した原価、「材料費」「労務費」「経費」 | |
| ・ 「材料費」「労務費」「経費」は機能(役割)でさらに分類できる | |
| ・ 製品の主原料の原価、「材料費」 | |
| ・ 人の賃金・給料の原価、「労務費」 | |
| ・ エネルギーや設備などの原価、「経費」 | |
| ・ 業種別に「材料費」「労務費」「経費」の構成を比べてみよう | |
| ・ 販売業やサービス業の原価は「仕入原価」と「労務費・経費」 | |
| ・ 製品との関係で分類した原価、「直接費」と「間接費」 | |
| ・ 原価の3要素を「直接費」「間接費」に分類すると? | |
| ・ 仕事量との関係で分類した原価、「変動費」「固定費」 | |
| ・ 管理責任で分類した原価、「管理可能費」と「管理不能費 | |
| column② 原価にならないお金(1) | |
| 第3章 原価計算のルールって? | |
・ 「財務諸表」でお金の流れを把握しよう |
|
| ・ 財務諸表には「損益計算書」と「貸借対照表」がある | |
| ・ 手持ちのお金の増減がわかる、「貸借対照表(BS )」 | |
| ・ 入ってきたお金と出ていったお金がわかるのが、「損益計算書(PL)」 | |
| ・ 「財務諸表」と「原価計算」のかかわりとは | |
| ・ 「内部統制」における原価計算の役割とは | |
| ・ 「モノづくりの流れ」で見る原価計算の役割とは | |
| ・ 原価計算の2つの流れ、「事前原価計算」と「事後原価計算」 | |
| ・ 事前原価計算で求める「見積原価」と「標準原価」 | |
| ・ 事後原価計算で求める「実際原価」 | |
| ・ では、「自分に必要な原価計算」は? | |
| column③ 原価にならないお金(2) | |
| 第4章 実際にかかった原価の計算方法 | |
| ― 実際原価計算・事後原価計算とは? | |
| ・ はるか昔からつづく「実際原価計算の決まりごと」とは | |
| ・ 「実際にかかった原価」を計算する流れ | |
| ・ 原価を「材料別」に集計してみよう | |
| ・ 材料が「在庫」として残ったらどう計算するか | |
| ・ 原価を「人別」に集計してみよう | |
| ・ 原価を「経費別」に集計してみよう | |
| ・ 原価を「部門別」に集計してみよう | |
| ・ 共通の原価を部門別に分ける「配賦」とは | |
| ・ 原価を「製品別」に集計してみよう | |
| ・ 「実際原価計算」にトライ! | |
| ・ 製造途中の「製品」はどう扱うのか | |
| ・ ここで「ABC」(活動基準原価計算)とはなにか | |
| ・ 原価を仕事の「内容別」に集計してみよう | |
| ・ 原価を作用する「コストドライバー」を発見しよう | |
| ・ 原価を「お客さま別」に集計してみよう | |
| column④ 会社の利益はどれくらいあるものなのか? | |
| 第5章 これからかかる原価の計算方法 | |
| ― 見積(標準)原価計算・事前原価計算とは? | |
| ・ 「見積原価計算」の流れ | |
| ・ 「製品1個の原価」を事前に計算しよう | |
| ・ 見積原価計算では原価を「材料費」と「加工費」に分ける | |
| ・ 「直接費・間接費」と「材料費・加工費」の関係を整理しよう | |
| ・ 詳細な材料費は「単価と消費量」で計算しよう | |
| ・ 「単価」を決定しよう | |
| ・ 「消費量」の内訳と計算方法とは | |
| ・ 詳細な加工費は「レートと時間」で計算しよう | |
| ・ 「レート」の内訳と計算方法とは | |
| ・ 時間の中身を「見える化」する | |
| ・ 「見積原価計算」にトライ! | |
| ・ 見積原価計算に役立つ道具、「コストテーブル」 | |
| ・ コストテーブルの「作り方」をマスターしよう | |
| column⑤ あるべき姿ってどんな姿? | |
| 第6章 原価計算を儲けにつなげるには? | |
| ・ 利益は「売上高」と「原価」で計算しよう | |
| ・ 変動費だけをとらえる「直接原価計算」と「限界利益」 | |
| ・ 「損益分岐点分析」で利益を見える化しよう | |
| ・ 変動費と固定費をとらえる「全部原価計算」と「粗利益」 | |
| ・ 「本当の赤字」と「見せかけの赤字」を区別しよう | |
| ・ 利益を生み出す「3つの作戦」を実践しよう | |
| ・ 原価計算で「コストダウンすべき製品」を発掘しよう | |
| ・ 「原価低減」による利益の生み出し方とは | |
| ・ 「企画・開発部門」の原価低減テーマと活動のすすめ方 | |
| ・ 新製品の原価低減効果は「見積原価」「目標原価」「標準原価」で把握しよう | |
| ・ 「仕入・製造部門」の原価低減テーマと活動のすすめ方 | |
| ・ 標準原価と実際原価の差を「原価差異」として把握しよう | |
| ・ 「原価差異の分析」にトライ! | |
| ・ 「営業・事務部門」の原価低減テーマと活動のすすめ方 | |
| ・ 原価管理の「PDCAサイクル」とは | |